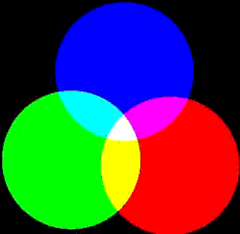 |
左の図は光の三原色とそれらを混ぜた状態を表している。光は重ねることにより元の色より明るくなり、すべての色を重ねると白色になります。 このような光による色の混合を加法混色と呼びます。 |
|
画面を作っています。 |
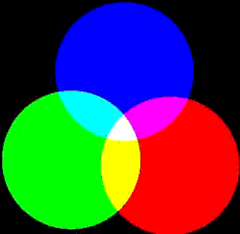 |
左の図は光の三原色とそれらを混ぜた状態を表している。光は重ねることにより元の色より明るくなり、すべての色を重ねると白色になります。 このような光による色の混合を加法混色と呼びます。 |
|
画像を印刷します |
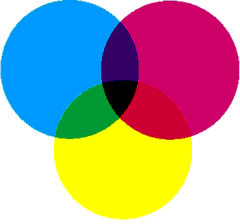 |
同様に左の図は色の三原色と混ぜたときの発色を表します。子供の頃絵の具を混ぜた色を思い出してください。きれいな色を作ろうと混ぜれば混ぜるほど黒に近づいていった経験はありませんか? このような色の混合を減法混色と呼び、光と正反対の性格であることがわかります。 |
|
|
| モニターの白はすべての色が発光する事で表現されますが、黒色の光という物はありませんので、すべての色を発光させないことで黒を表現します。つまり電源を切った時のモニターの表面の色が実際の黒色となりますが周りが発光しているので実際よりもより黒くみえます。 では、印刷物の白はどうでしょう?そうです紙の色つまりなにも塗って無い状態が白色ですね。ですから印刷に使用する紙によって、できあがりが変わってくるのはそのせいです。また、三原色を混ぜただけでは完全な黒にはならないので実際の印刷には三原色に黒を加えた4色インクを使用しています。色の名前も子供の時にならった青、赤、黄とは呼ばずにシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)と呼ぶようになっています。 このようにお互いに反対の性格を持つ物同士を使って同じ色を出すのは大変なことですよね。 |